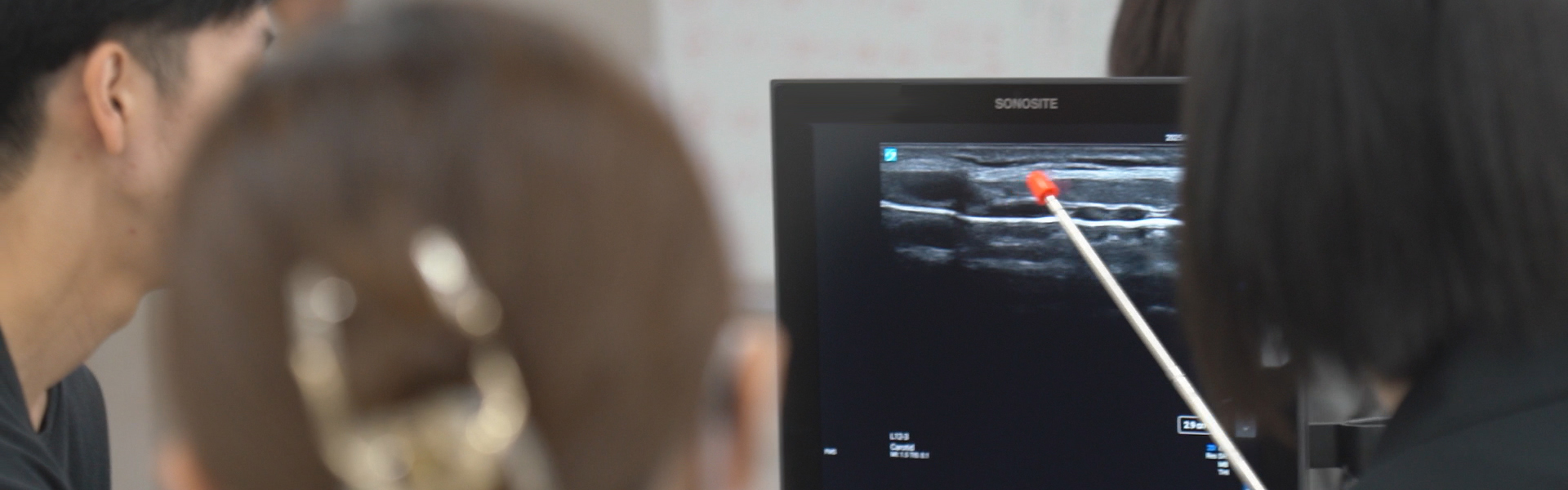1. 基礎研究
麻酔科学は手術時の痛みを克服するために生まれた学問です。私たちは、末梢でどのように痛みが感知されるか、脊髄でどのように痛みが修飾されるか、脳でどのように痛みが認知されるか、を動物・ヒトで研究しています。 最近では、がんの痛みの研究を進め、これまでブラックボックスであったがんの痛みのメカニズムを明らかにするとともに、新たな治療法を探索しています。

(1)痛みの研究
-
術後痛・外傷後痛の機序解明・・・軽微な刺激で強い痛みが発生する機序の解明
手術後痛や外傷後痛では、呼吸・咳嗽を含む日常動作やガーゼ交換など軽微な機械刺激によって生じる強い痛み(機械性痛覚過敏/アロディニア)である。これらは、ADL/QOLを低下させるとともに、リハビリテーションを妨げ、早期回復の阻害因子となり得る。
当教室では、手術後・外傷後の急性期に軽微な機械刺激によって生じる強い痛みの責任分子としてTmem45bを世界に先駆けて発見した。現在、Tmem45bを中心に軽微な機械刺激によって生じる強い痛みの分子メカニズム解明とそれを基にした創薬をテーマーに研究を進めている。
- Tanioku T et al. Tmem45b is essential for inflammation- and tissue injury-induced mechanical pain hypersensitivity. Proc Natl Acand Sci USA 2022; 119:e2121989119
-
がん性疼痛の機序解明
抗がん剤の発達によりがん患者の予後は延長し、痛みをはじめとするがんに伴う症状のコントロールが一層重要となっている。当教室では、これまでに骨がん痛やがん転移痛について動物モデルを作成し、その機序の解明を行ってきた。現在、“知覚神経とがん細胞増殖の相互作用に注目し、がんの増大が痛みを発せさせる”のではなく、“痛みががんを増大させる”との仮説のもと研究を進め、新たな機序解明を進めている。

- Yoshida A et al. Neuroscience 2024; 538: 80-92
- Fuseya S et al. Anesthesiology 2016; 125:204-18
-
慢性疼痛患者における脳内ネットワークの機能的変化
非侵襲的な手法である機能的MRIを用い、ヒトにおいて慢性疼痛が脳内ネットワークの可塑的変化に及ぼす影響を調査している。帯状疱疹後神経痛患者と健常人との比較や、帯状疱疹後神経痛とうつ病患者の共通した神経基盤を探索している。また、神経障害性疼痛と、比較的新しい概念である痛覚変調性疼痛との患者間の比較も試みている。 また、産科麻酔領域で中枢神経系が原因となりうる疾患に注目して機能的MRIを用いて前頭葉領域のネットワークの変化を探索している。

- Kurosaki H et al. PLoS One 2018; 13:e0203067
-
麻酔薬と血管内皮グリコカリックス
血管内皮細胞の内膜面には内皮グリコカリックスとよばれる糖鎖の層が存在する。内皮グリコカリックスは、第1に透過選択性のある防護壁として、第2に酵素、補酵素、液性伝達物質の局所濃度調節領域として、第3にシェアストレスといった物理的刺激のシグナル伝達経路の一部として働いている。内皮グリコカリックスが障害されると、内皮機能障害を引き起こすこととなる。私たちはこれまでにラット摘出血管を用いてセボフルランが内皮グリコカリックス障害を回復させることを示した。現在、内皮グリコカリックスの障害および回復に焦点をあてて、その機序の解明に取り組んでいる。

- Kazuma S, Tokinaga Y, et al. J Surg Res. 2019; 241:40-47.